| 日刊北海協同組合通信連載ロングラン企画 | ||||
| 「水曜インタビュー」 ~今知りたいテーマを1番近くにいる人に聞く~ | ||||
| 「水曜インタビュー」バックナンバー |
||||
| 10月15日掲載 | ||||
| 西川 孝範 | JAきたみらい代表理事組合長 | |||
 |
☆営農指導を強化、ピンチを変革の好機に ▽独自の営農緊急支援対策で1・5億円計上 ▽2・7億円を期中還元、土壌分析体制も強化 ▽センター方式を採用し「出向く営農」へ ▽土壌診断結果のデータもとに適正施肥を指導 ▽新銘柄の開発を継続、堆肥利用は今後の課題 ▽値上げ影響大の多肥作物―てん菜、たまねぎ ▽たまねぎ専業も交換作付け、輪作で増収効果 ▽国民の理解得て大豆を増産、輪作体系に ▽24億円の7割補てん、財源不足の懸念 |
|||
| 10月8日掲載 | ||||
| 飯澤 理一郎 | 北海道大学大学院農学研究院教授 | |||
 |
☆農業立県・北海道からのメッセージを ▽毎年6000万㌧の食料を輸入する国 ▽輸出国は偏在し、貿易量の底も浅い ▽自給率向上が担保する5つの安全性 ▽国産を少し高く買うことは、未来への保険 |
|||
| 10月1日掲載 | ||||
| 金川 幹司 | 北海道酪農協会会長 | |||
 |
☆消費者、乳業の理解得て次のステージへ ▽食べものの大切さが骨身に染みた青春時代 ▽地球が人間で溢れる ▽酪農の仕事は食料と国土を守る ▽本州と北海道がバランスある発展を ▽酪農の衰退は国家的損失、食い止めよ ▽酪農基盤維持のために躊躇するな ▽マイナス増えたら北海道も不安定に ▽飼料自給率向上に支援急げ |
|||
| 9月24日掲載 | ||||
| 中原 准一 | 酪農学園大学環境システム学部教授 | |||
 |
☆WTO交渉決裂と今後の北海道農業 ▽理想主義的色彩が強いGATTの発足 ▽欧州のCAPから始まったダンピング競争 ▽アメリカとEUがつくったUR合意 ▽先進国と途上国、そしてブラジルとインド ▽重要品目4%+2%、MAの拡大が問題に ▽アメリカの国内支持削減も大きな焦点 ▽国内支持に見る、URとドーハの違い ▽多様な農業の共存―政策的裏づけが必要 |
|||
| 9月17日掲載 | ||||
| 飛田 稔章 | JA道中央会会長 | |||
 |
☆自給率向上へ、消費者理解と国の支援を ▽産地廃棄、消費者の「もったいない」を意識 ▽WTO交渉、決裂状態からのスタートに懸念 ▽資材価格高騰―対策本部設置し、要請強化 ▽不正規流通米は消費者への裏切り行為 ▽グローバル化に打ち勝つ経営をどうつくるか |
|||
| 9月3日掲載 | 服部 昭久 | JAめむろ管理部共済課渉外係長 スーパーライフアドバイザー |
||
 |
☆共済はまず仲良く、一発大物は狙わず ▽全道一位目指す切っ掛けは2人目の子ども ▽つながりを有効に生かして営業 ▽打ち解けるのが先。決して先を急がず ▽内なる切っ掛け、動機を明確に ▽成績にむらを作らないように ▽表彰よりもお客様が最も大事 |
|||
| 8月27日掲載 | 林 美香子 | ホクレン員外監事 慶応義塾大学大学院教授 |
||
 |
☆地域の資本を生かす「農都共生のススメ」 ▽「農都共生」が注目される3つの理由 ▽九州のツーリズム大学―熊本県小国町 ▽人材育成と地産地消―帯広「北の屋台」 ▽常連客の会話が屋台の人気メニューに ▽地域の資本を生かす、そのためのヒント ▽チーズと観光が農村を支える―フランス ▽シャッター通りに直売所、身近な連携から |
|||
| 8月20日掲載 | ||||
| 佐藤 雅仁 | JA鹿追町代表理事組合長 | |||
 |
☆農家経済の厳しさとJAの対応 ▽肥料価格は平成18年から上昇 ▽飼料代が350万円も増加、影響厳しく ▽組合員に3億9000万円を還元 ▽ヘルパー、コントラなどで経営支援 ▽国の支援、生産者の努力が不可欠 ▽価格転嫁はバランスに配慮して |
|||
| 8月13日掲載 | ||||
| 大西 昭男 | JAびえい代表理事組合長 | |||
 |
☆「美瑛選果」核に、さらなるブランド力を ▽WTO交渉、政府は明確な方針示すべき ▽ブランド化に向けた土づくりと人材育成 ▽レストランは有名シェフ・中道博氏と提携 ▽サミットでもアピール、ブランド化さらに ▽バイヤーが直接来店、販路拡大の窓口に ▽資材高騰で独自対策も検討、農協の原点に ▽経営所得安定対策、仕組みに課題も ▽肥料価格が高騰、てん菜の作付減が懸念 |
|||
| 8月6日掲載 | ||||
| 飛田 稔章 | JA道中央会会長 | |||
 |
☆輸出国主導のWTO、日本は戦術見直せ ▽交渉の基調、日本の姿勢に課題 ▽決裂を喜んでばかりはいられない ▽本当の国益は何かを議論すべきだ ▽世論喚起し、食料の大事さを訴えたい ▽政府は交渉戦術練り直せ ▽農業者の努力と政策支援で体質強化 |
|||
| 7月30日掲載 | ||||
| 中田 清志 | ㈱ホクレン商事社長 | |||
 |
☆生産者に最も近い食品スーパーとして ▽Aコープのレギュラー化を目指し合併 ▽旧3社の店舗をレベルアップ、平準化が急務 ▽消費マインドの抑制とコスト要因が浮上 ▽大手流通と体力勝負、4番目の土俵目指す ▽3カ年計画で具体的なコンセプトを提示 ▽Aコープへの支援で新たな役割も ▽食育や地産地消など、消費者への発信も ▽消費者理解追い風に、加工食品開発にも意欲 |
|||
| 7月16日掲載 | ||||
| 鈴木 宣弘 | 東京大学大学院教授 | |||
 |
☆新たな指標の下、支え合う社会の実現を ▽輸出規制は不安心理で簡単に起きる ▽食料の海外依存に楽観的だった日本 ▽日本が過保護で閉鎖的というのは間違い ▽競争力があるから輸出国になったのではない ▽食料生産がいかに大切か―欧米の農業政策 ▽経済界からの貿易自由化圧力、未だ衰えず ▽西オーストラリアの平均規模は5800㌶ ▽窒素循環から考える国内農業の大切さ |
|||
| 7月9日掲載 | ||||
| 橋本 智子 | 北海道消費者協会会長 | |||
 |
☆努力した生産者を買い支えていく消費者に ▽消費者行政の転換期、地元の声を伝えたい ▽自給率200%なのに、農業経営は大変 ▽環境問題が影響、生産コストの上昇どこまで ▽安全・安心、コストのことを考える消費者に ▽どちらを選ぶかは消費者の権利―原産地表示 ▽開放系でのGM作物栽培は、なお慎重に |
|||
| 6月25日掲載 | ||||
| 越後 功 | JA道青年部協議会会長 | |||
 |
☆盟友と国民にメッセージを伝えたい ▽メッセージを届けたい―会長就任を決意 ▽「農奴になるな」―人間性の幅を広げてほしい ▽不眠不休で圃場の排水性向上に取り組む ▽担い手育成面で薄まった―農政改革 ▽全菓連青年部との交流でシュマリを斡旋品種に ▽リスク恐れずに行動できるのが青年部 ▽1人10人への声掛けをノルマに―街頭活動 |
|||
| 6月11日掲載 | ||||
| 信﨑 健一 | 雪印乳業CSR推進部長 | |||
 |
☆倫理観を徹底し、企業の社会的責任果たす ▽環境保全型の大規模農業進める土台づくりを ▽土も水も両方がクリーンでなければいけない ▽洞爺湖サミット、ターゲットは各国メディア ▽生産者の「もう1歩」を後押ししていきたい ▽地元食材活用、地産地消の料理で地域交流も |
|||
| 6月4日掲載 | ||||
| 高田 勝弘 | 道酪農協会常務理事 | |||
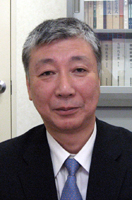 |
☆多種多様な酪農経営が並存できるように ▽身が引き締まる緊張感を味わっている ▽酪政連の役割の大きさ再認識を ▽政治の役割重要、国会に応援団育てたい ▽中長期需給変動へのリスクヘッジ重要 ▽食料自給は喫緊の課題 |
|||
| 5月28日掲載 | ||||
| 櫻庭 英悦 | 北海道農政事務所長 | |||
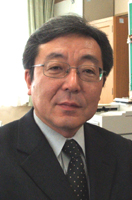 |
☆日本農業を牽引する食料供給基地・北海道に ▽参事官として食料・農業・農村基本計画を担当 ▽食料自給率の向上には、長期的な分析が不可欠 ▽国産に追い風、今こそ道農業の再点検が必要 ▽制度は変わるもの、今後も現場の声を ▽統計調査、要望あればノウハウ提供したい ▽新たに「農商工連携」や「リサイクル」も |
|||
| 5月21日掲載 | ||||
| 森江 義信 | ホクレン米穀事業本部長 | |||
 |
☆播種前契約で産地と実需の結び付きを強化 ▽販売企画部長を務め、供給責任の重要性を実感 ▽米粉、飼料など新規需要で水張り面積守りたい ▽北海道米は1番下の棚から脱出した段階 ▽生産費上昇に理解―20年産播種前契約 ▽運賃安い道内販売最優先、道外は顧客絞り込み ▽「直売の代わりに播種前契約」も選択肢に ▽今後の販売を左右する品種―上育453号 ▽全用途提供可能な品揃えをさらに強化 ▽産地が価格決定に参画できる4者契約は画期的 |
|||
| 5月14日掲載 | ||||
| 細越 良一 | 北海道農政部長 | |||
 |
☆生産者と直接対話、現場主義に徹したい ▽環境保全型の大規模農業進める土台づくりを ▽土も水も両方がクリーンでなければいけない ▽洞爺湖サミット、ターゲットは各国メディア ▽生産者の「もう1歩」を後押ししていきたい ▽地元食材活用、地産地消の料理で地域交流も |
|||
| 4月23日掲載 | ||||
| 谷村 知重 | 美唄市水稲直播研究会会長 | |||
 |
☆高収量・良食味のほしまるで直播普及に拍車を ▽ほしまるは14㌶増の41㌶に―20年産 ▽700㌔を目標にできるレベルに ▽雑草対策が最大の課題、初期投資もネックに ▽直播導入によりアスパラで複合化、1㌶まで拡大 ▽ほしまるで全道統一ブランドを展開したい ▽20年産からYES!clean栽培がスタート |
|||
| 4月16日掲載 | ||||
| 川成 眞美 | 雪印乳業専務北海道本部長 | |||
 |
☆「健土健民」が北海道本部の基本理念 ▽北海道は原料調達の最重要拠点 ▽チーズは北海道での事業の柱 ▽機動性、機能性、スピード感高める ▽本州酪農を軽視する考えは毛頭ない ▽生処連携して国産原料に回帰を促進 ▽お金を出せば輸入できる時代終わった ▽加工原料乳のあり方、真剣な検討を |
|||
| 4月9日掲載 | ||||
| 山田 富士雄 | 北海道農民連盟委員長 | |||
 |
☆輸入ありきは失政、自給率向上こそ至上命題 ▽「農業をよくしたい」との思いで運動に ▽総会は例年にない活気、系統への意見も ▽品目横断への批判、3者合意に疑問の声 ▽農政改革の前に、食料政策を示すべき ▽54年の食料援助、60年の自由化が引き金に ▽WTOよりも国内の食料政策充実が先決 ▽ルールを変えるためには政治的な力が必要 |
|||
| 3月26日掲載 | ||||
| 西村 和雄 | 有機農業技術会議代表理事 | |||
 |
☆有機農業再考論―本物の有機農業を目指して ▽土壌や作物の分析技術開発を急ぐべき ▽代替資材に依存した有機農業に警鐘 ▽低投与型から低栄養生長、それが本物 ▽有機農業の定義を明確化―今後の課題 |
|||
| 3月12日掲載 | 菊地 稔 | JAオホーツク網走代表理事組合長 | ||
| オホーツク農協組合長会会長 | ||||
 |
☆地力維持が農業の基本、緑肥の積極導入を ▽農協合併、将来的に斜網は1本化目指すべき ▽小麦の見直し、基準年の是正が不可欠 ▽品目横断の問題点―野菜へシフトが悪循環 ▽休閑緑肥の効果を検証、改めて予算化を ▽飼料対策は5月末、「真水の対策」かなわず ▽ブロック制から地区推薦へ―道連の役員改選 ▽共同化でコスト低減し、土づくりに力を |
|||
| 3月5日掲載 | ||||
| 飛田 稔章 | JA道中央会副会長 | |||
 |
☆課題は残っているが、一定の土台築ける ▽乳業との交渉結果を踏まえて運動した ▽政策支援の重要性は非常に高かった ▽さらなる手取りのアップが必要 ▽肥育牛に対する物財費6割補てんは実質8割 ▽新規リース事業の活用を ▽決定をバネに経営改善努力 ▽価格転嫁への消費者理解、今後も努力必要 |
|||
| 2月27日掲載 | ||||
| 新井 光雄 | JA上川中央代表理事組合長 | |||
 |
☆地域と共生し、幸せになれる仕事に努めたい ▽研究会から15年、協議難航で2JAが先行 ▽先延ばしできない、先行してやろう ▽組織体制・役員数など、経営体として判断 ▽組合員の高齢化、大胆な組織変わりが必要 ▽5JAの枠組み、これで終わりではない |
|||
| 2月20日掲載 | ||||
| 田中 一生 | 北海道立中央農試水田・転作科長 | |||
 |
☆19年産米作柄の分析―冷害は回避できたか ▽7月の低温は全道的、プラス寡照で作柄悪化 ▽寡照で効果弱まるが、深水管理は必須 ▽水管理、熟期分散などで収量をカバーした農家も ▽低米価が農家意識に格差もたらす ▽ここ数年は早生品種の冷害被害大きい ▽「コシヒカリに追いついた」は早計 ▽収量と食味を両立させた初の品種―ななつぼし ▽食味向上は明治から始まる品種改良の成果 |
|||
| 2月13日掲載 | ||||
| 石橋 榮紀 | JA浜中町代表理事組合長 | |||
 |
☆情勢変化に敏感になって難局を乗り切ろう ▽茹で蛙になるな、経営を引き締めよ ▽飼料価格の高騰でJAが対応 ▽JA合併、最後は人間関係 ▽レベルの高い営農指導を追求したい ▽新規事業を浸透させるカギは女性 ▽ハーゲンダッツへの供給は誇り ▽需給変動の先読みは重要 ▽地域貢献の一環で高齢者の集いに支援 |
|||
| 1月30日掲載 | ||||
| 中川昭一衆議院議員・寺島実郎日本総研会長 | ||||
 |
☆対談―北海道を再びエネルギーの島に ▽バイオエネルギーめぐる3人の恩人―中川氏 ▽日本型の環境にやさしいエネルギーをつくる ▽話題提供から10年、よくここまできた―寺島氏 ▽環境、農業、エネルギーをつなぐシナリオ ▽農業基盤の重要性、CO2吸収でも再評価 ▽実証実験から産業化の段階へ、潜在需要は大 ▽1990年が基準、日本はハンディがある ▽非食用部分の活用に向け、段階的に接近 |
|||
| 1月23日掲載 | ||||
| 長谷川 敦 | 農畜産業振興機構国際情報審査役 | |||
 |
☆世界の酪農と牛乳・乳製品事情 ▽米政権の中東原油依存脱却が発端 ▽結局コストに見合うかどうかが分かれ目 ▽GM技術でとうもろこしの作付け増 ▽日本は牛肉、鶏肉輸入の偏りに注意 ▽投機筋の介入で需給実勢以上に高騰も ▽世界各国の原料生乳価格は大幅上昇 ▽乳製品貿易ではNZの戦略注視を ▽特定国の事情、思惑で市況が動く ▽日豪EPA交渉、議論かみ合うはずがない ▽NZの世界市場におけるシェアはさらに拡大か |
|||
| 1月16日掲載 | ||||
| 鈴木 宏一郎 | ㈱北海道宝島旅行社代表取締役社長 | |||
 |
☆農家民宿とGTで農業、農村を豊かに ▽農業分野のコンテンツ充実したい ▽パック旅行ではみな疲弊する? ▽滞在型・体験型を検索するシステム立ち上げ ▽北海道は最高のGTを展開できる ▽ありのままを見てもらうのが大切 ▽JAと地域リーダーが重要な役割 |
|||
| 1月9日掲載 | ||||
| 宮田 勇 | JA道中央会会長 | |||
 |
☆平成20年を北海道農業発展の年に ▽北海道農業への国民の期待に応えたい ▽重要品目数の分母、有税はカッコ書きに ▽平成20年は「展」を象徴する字に |
|||
| 12月19日掲載 | ||||
| 長井 昭彦 | 裕毛屋複合物流総部総経理 | |||
 |
☆北海道のこだわり商品を台湾に届けたい ▽SARSを契機に、屋台から食品が消えた ▽生産履歴がしっかりした信用できる商品 ▽新幹線の開通が食文化を大きく変えた ▽小売業界は飽和状態、さらなる差別化が必要 ▽少子高齢化と女性の社会進出が大きな要素 ▽日本の食材、意外と食べ方を知らない ▽北海道の景色が生産者の信用につながる ▽継続することが大切、物産展の見直しを ▽年間通じたプロモーションでもっと伸びる ▽自ら現地を研究し、販売戦略持つことが重要 |
|||
| 12月12日掲載 | ||||
| 筒井 信隆 | 衆議院議員(民主党NC農水大臣) | |||
 |
☆民主党農業者戸別所得補償法案について ▽農業は市場原理一本槍ではやっていけない ▽多様な取り組みを規模に関わらず支援 ▽農業の多面的機能の評価も盛り込む ▽米も所得補償の対象、生産目標順守が要件 ▽米の生産目標は上限、米以外は下限が基本 ▽現行対策より生産目標に従うメリット大きい ▽5階建てで政策誘導明確に、ばらまきではない ▽現行予算枠組みを根本から変え、1兆円を捻出 ▽自民党の「自由化前提」批判は曲解 |
|||
| 12月5日掲載 | ||||
| 原 俊作 | JA道央代表理事組合長 | |||
 |
☆道央農業振興公社を核に地域農業発展図る ▽まずは人事交流に着手、旧JA色を克服 ▽管内全市に直売所開設、野幌は倍増 ▽Aコープ、スタンドはなかなか厳しい ▽振興公社が5つの事業を柱に地域農業に寄与 ▽酪農学園との協定は先駆的、意欲的 ▽4JAが互いに中身を知り合い、次の合併へ ▽出荷努力で道産米販売に貢献したい |
|||
| 11月28日掲載 | ||||
| 柳 在相 | 日本福祉大学教授 | |||
 |
☆魅力あるJAを創るための戦略的マネジメント ▽戦略とは、環境変化に適応するための努力 ▽なぜ、JAは経営改革が進まないのか ▽戦略なき組織は滅びる、非営利組織も同じ ▽形式的な平等より、実質的な公平が必要 ▽理念があっても経済がなければ意味がない ▽農業の工業化、IT化で付加価値高める産業に ▽明るいビジョン提示し、意識改革進める ▽農業もマーケティングの時代、消費者志向へ ▽戦略課題をどう解決するか―先進事例から ▽盛り上がった組織は強い、経営者は火付け役 |
|||
| 11月21日掲載 | ||||
| 岩崎 充男 | HAL財団・流通開発部長 | |||
 |
☆流通・販売に新たな道を開くため ▽HAL認証と北海道農業・元気プロジェクト ▽貯蔵から選果、小分けまで自己完結する施設 ▽CA貯蔵完備、いも・たまの長期貯蔵も可能 ▽取扱高は約10億円、需要あるが供給体制まだ ▽目的は北海道農業の活性化、贅沢品は不可 ▽安全でもおいしくなければ供給してはいけない ▽ポジティブリストの210成分を検査 ▽省力化と多機能を兼ね備えた、屈指の選別機 ▽地域農業を守る志があれば、結果はついてくる |
|||
| 11月14日掲載 | ||||
| 宮田 勇 | JA道中央会会長 | |||
 |
☆緑ゲタ、米生産調整で本道の主張を強く訴える ▽政府米緊急買い入れ、公平な配分求める ▽是正緑ゲタ単価の今年産からの適用を ▽過去実績の固定化は転作促進の流れに矛盾 ▽タリフライン総数が分母の重要品目数算定求める |
|||
| 11月7日掲載 | ||||
| 三輪 茂 | 日高町長 | |||
 |
☆馬産地一体となって北海道競馬の存続目指す ▽産地主体の新公社設立、開催は門別に集約 ▽北海道競馬の廃止は国内競馬全体の縮小招く ▽20年度内に組織づくりと施設整備を完了 ▽ノウハウ持つプロパー招き即断即決で事業展開 ▽集約開催による経費節減は2・3億円 ▽施設整備に重い負担も覚悟を決めて臨みたい ▽北海道競馬を継続し多様な馬文化守る |
|||
| 10月31日掲載 | 本田 廣一 | 北海道の有機農業を進める会副代表 | ||
| ㈲興農ファーム代表取締役社長 | ||||
 |
☆国民の圧倒的支持が得られる北海道農業に ▽超党派の議員立法で有機農業推進法が成立 ▽議員連盟と民間の全国運動が合致し急展開 ▽推進法は理念法、農業者などの自主性を尊重 ▽環境負荷を抑え、生物の多様性を生み出す ▽有機農業との深い縁、北海道こそメッカに ▽個人レベルの技術を集約・検証し、普及へ ▽農業こそ日本の宝、官民協同でつくり上げ |
|||
| 10月24日掲載 | ||||
| 児玉 芳明 | ㈱北海道フットボールクラブ代表取締役社長 | |||
 |
☆JAグループ北海道と連携し食育推進を加速 ▽子どもの未来に農業の発展は欠かせない ▽サッカー教室で子どもの食の実態を知る ▽コンサドーレのノウハウを広く伝えたい ▽環境保護の観点からも地産地消を推進すべき ▽消費者の理解得られればコストは払ってくれる ▽サッカー&食育教室でごはんの力訴える ▽選手に田植え、稲刈りなど農業体験も ▽天然芝は人を元気にさせる―農業にも同じ力 ▽筆頭株主が企業でないのはJリーグ唯一 ▽総合スポーツクラブづくり進め、底辺広げたい |
|||
| 10月17日掲載 | ||||
| 竹林 孝 | 道農政部食の安全推進局長 | |||
 |
☆BSE問題の議論を深めよう ▽全頭検査は混乱沈静化に大きな役割発揮した ▽まだ十分理解、浸透していない ▽EUの検査目的はモニタリング ▽リスク評価を改めて受け止めたい ▽消費者にていねいな説明何より重要 ▽病気メカニズムの解明、確実に進んでいる ▽リスクレベルと費用負担、冷静な論議を ▽混乱は回避しなければならない |
|||
| 10月10日掲載 | ||||
| 加賀爪 優 | 京都大学大学院農学研究科教授 | |||
 |
☆豪州農業および農業政策の特質と今後の展望 ▽60年ごろから農業のシェアが激減 ▽80年代初頭に規制緩和と民営化を断行 ▽戦後最大の干ばつで農場負債が累増 ▽小麦ボードのプール制度に輸出補助効果の批判 ▽一元的輸出権限の継続は困難、競争力も低下 ▽豪州の農業地帯は人工的につくられた ▽77年のRASで支援対象を絞り込む ▽免税預金制度で豊凶変動の影響を軽減 ▽連邦政府が情熱を注ぐのは対中FTA ▽西豪州のバイオF戦略が日本の小麦輸出に影響 ▽連邦政府と州政府は歴史的に非協調 |
|||
| 10月3日掲載 | 中原 浩一 | ㈲NKファーム代表取締役 | ||
| ㈲フードライフ代表取締役 | ||||
 |
☆直売所を消費者交流と農産物評価の拠点に ▽品目横断見据え、複数戸法人設立 ▽コンバインを2台処分も作業に支障なし ▽団地化で省力化と農薬飛散リスク低減 ▽無農薬などの努力は直売所で訴えるのが1番 ▽自己資金3割と道補助と信金融資で費用賄う ▽直売所を地域密着型消費者交流の場に ▽量販店に出店、割高でも連日完売 ▽直売所部門で前年売上1・5倍目指す ▽組合員に利益が出れば、農協も潤うはず ▽上川産ではなく共励会受賞豚肉として販売 |
|||
| 「水曜インタビュー」バックナンバー | ||||