| 日刊北海協同組合通信連載ロングラン企画 | ||||
| 「水曜インタビュー」 ~今知りたいテーマを1番近くにいる人に聞く~ | ||||
| 「水曜インタビュー」バックナンバー |
||||
| 12月20日掲載 | ||||
| 金川 幹司 | 道酪農協会会長 | |||
 |
☆全国民を巻き込んだ猛烈な運動を ▽FTAを急ぐ背景にASEANの主導権争い ▽2年間に及ぶ共同研究が土台に ▽風穴が広がるのを避けたい ▽道庁の影響試算は強い危機感の表れ ▽豪州にとって農業なしの交渉にメリットなし |
|||
| 12月13日掲載 | ||||
| 佐藤 茂 | JA鹿追・前代表理事組合長 | |||
 |
☆JAは「真面目な者」の味方だ ▽農協との出合いは18歳、創立総会へ出席 ▽太田寛一、梶浦福督という個性の影響 ▽素材豊富な十勝、良い材料はたくさんある ▽理論武装して政策提言―がスタイルに ▽農協の経営危機から得た教訓と決意 ▽手づくりの振興計画は組合員との契約書 ▽営農推進体制の確立が系統利用につながる ▽農協だよりを直接配布、地域へ情報発信 ▽部落懇談会は職員が自分を売り込む場 ▽コネは一切なし、人事では鬼になれ ▽望まれるトップ、理想的な親父像を目指して ▽疾風にして勁草(けいそう)を知る ▽JAは決して弱い者の味方ではない |
|||
| 12月6日掲載 | ||||
| 白川 祥二 | 道農連書記長 | |||
 |
☆地域の活性化が大前提、予算確保に努力を ▽環境保全向上対策、再度地域で話し合いを ▽メニューは自由、地域からの逆発信が重要に ▽実験事業活用し、離農跡地を優良農地に ▽中山間直接支払は本来の条件不利対策へ |
|||
| 11月29日掲載 | ||||
| 武田 泰明 | 日本GAP協会事務局長 | |||
 |
☆GAP全般とJGAPについて ▽PL制度導入でGAP導入の必要性が高まる ▽生産者として当たり前の128の適合基準 ▽適合基準に基づき各農場でマニュアル作成 ▽出荷時の農薬付着などリスクを想定し改善 ▽農場管理のプロが審査、客観的証明に ▽認証により作業の効率化も実現 ▽GAPで安全確保、トレサで安心伝える ▽JGAP含め国内に5種類のGAPが存在 ▽農家がGAPの重要性実感、協会設立へ ▽欧州ではユーレップ認証が必須 ▽GAP乱立状態は生販に負担 ▽日本でもイオン、生協とともに標準化の動き |
|||
| 11月22日掲載 | ||||
| 宮田 勇 | JA道中央会長 | |||
 |
☆組合員と食料支える活力あるJAづくりに邁進 ▽グループの総力結集、決議の実践を ▽日豪FTA緊迫、関税撤廃なら壊滅的 ▽農業経営ステップアップなど5つの基本方針 ▽協同組合理念の徹底、競争力ある事業方式 ▽JAグループへの結集、農政で特別決議 |
|||
| 11月15日掲載 | ||||
| 小池(相原) 晴伴 | 酪農学園大学農業経済科助教授 | |||
 |
☆産地の努力生かすには全体需給調整が大前提 ▽ホクレンの全道共販が基本 ▽全道共販への再結集は当然の方向 ▽全国的な出荷調整の仕組みが必要 ▽産地の努力生かすには全体需給調整が大前提 ▽県連間で販売計画を共有し調整し合うべき ▽全国的な相場確立されれば、統制ある販売に ▽価格形成における品質評価と需給反映が混乱 ▽新需給調整システムは実態に即していない ▽配分は上からの流れで従来と変わらず ▽全体需給の調整を念頭に販売拡大の推進を |
|||
| 11月8日掲載 | ||||
| 木下 寛之 | (独)農畜産業振興機構理事長 | |||
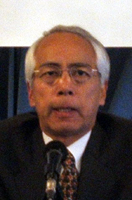 |
☆最近の農業情勢をめぐる情勢について ▽日本の農産物の関税は世界的にみて低い ▽豪州などの輸出奨励措置を問題視 ▽青の政策の削減も議論の対象に ▽複雑に絡み合う各国の利害をどう調停 ▽国内支持、平均削減率50%の提案も ▽産業界はEPA・FTAに傾斜 ▽豪州は関税撤廃対象で厳しい提案 |
|||
| 11月1日掲載 | ||||
| 宮田 勇 | JA道中央会会長 | |||
 |
☆バイオエタノール事業でCO2削減に寄与 ▽JA道大会で農業振興とJAの発展期す ▽生乳計画生産に向け、取り組み強化 ▽Bエタノール工場、CO2削減に寄与 |
|||
| 10月25日掲載 | 余湖 智 | ㈲余湖農園取締役 | ||
| ㈱グローバル自然農園代表取締役 | ||||
 |
☆原点は産直、そして担い手育成を目的に ▽消費者も出資、平成3年に販売会社を設立 ▽米から野菜、特別栽培・産直へ―2度の転機 ▽販売が軌道に、断腸の思いで産直を休止 ▽独立後の販路確保、グループでブランド形成 ▽30種類の多品目生産、80人体制でもまだ足りない ▽独自農法を研究、根こぶ病への微生物利用も ▽有機認証取得はコスト3割増、マーケット失う ▽運転資金はクミカン、限度額は4000万円 ▽北洋銀行が融資提案、クミカンに代わるものを ▽使いやすい商品メニュー、全国初のケースに ▽プロに経営をチェックしてもらうチャンス ▽考え方を改めてもらう契機になれば |
|||
| 10月18日掲載 | ||||
| 髙橋 俊一 | JAきたみらい代表理事組合長 | |||
 |
☆てん菜の生産縮小は自給率下落の象徴だ ▽現状では64万㌧以上は自粛するしかない ▽「全道一律」に、北見地区からは反論も ▽注目の指標面積、あまりこだわらないのでは ▽たまねぎへの転換増、加工対策の成果を重視 ▽利害が絡む中での糖区廃止、大変なことだ ▽早期出荷は糖業の理由、基金活用には疑問も ▽異性化糖などの輸入を抑制、真の担い手対策を |
|||
| 10月11日掲載 | ||||
| 齋藤 京子 | 農水省中国・四国農政局次長 | |||
 |
☆農村の実態に思いを馳せる消費者に ▽農場と食卓の距離拡大がもたらす問題を指摘 ▽国内農業だけでは献立はいもとごはんばかりに ▽耕作放棄地の増大、深刻化 ▽子どものころの食習慣、生涯に影響 ▽リスク管理と生産振興を独立した機関で ▽農業体験で生産現場の実態を理解してほしい ▽どこまでゼロリスク追求するか ▽生産の苦労に思い馳せる「心で食べる時代」に |
|||
| 10月4日掲載 | ||||
| 磯田 憲一 | 農業企業化研究所理事長 | |||
 |
☆道農業の企業的展開のため選択肢を提示する ▽農業の潜在能力を引き出したい ▽あくまでも多様な選択肢のひとつを提案 ▽栽培協定に結集、新しい流通チャネルに挑戦 ▽恵庭に物流拠点、来年夏稼働 ▽BSE発生は安全確保で大きな教訓 ▽科学的見地で消費者心情鎮まらず |
|||
| 「水曜インタビュー」バックナンバー | ||||