| 日刊北海協同組合通信連載ロングラン企画 | ||||
| 「水曜インタビュー」 ~今知りたいテーマを1番近くにいる人に聞く~ | ||||
| 「水曜インタビュー」バックナンバー |
||||
| 9月27日掲載 | 宮田 勇 | JA道中央会会長 | ||
| 矢野 征男 | ホクレン会長 | |||
 |
☆当面する農政課題への対応 ▽経営安定対策の面積カバー率9割 ▽豪州とのEPA交渉、影響を懸念 ▽農薬残留、風評被害防止に迅速・的確情報を ▽エタノール実証プラントを十勝で ☆道産米、牛乳販売に全力 ▽18年産米、実需直結型の販売推進を継続 ▽道内販売8・8万㌧、食率66%を計画 ▽道産生乳の道外消費、25カ月ぶりに前年超 |
|||
| 9月20日掲載 | ||||
| 山本 勝博 | JA中札内村代表理事組合長 | |||
 |
☆枝豆生産に意欲、販売強化は職員教育から ▽平成4年にスタート、我慢を重ねて今日まで ▽10億かけて工場増改築、面積は220㌶に拡大 ▽収穫から4時間以内に―日生協の要望を実践 ▽2台の専用コンバイン、残留農薬検査も徹底 ▽10月4日には焼酎など枝豆加工品も販売開始 ▽品目横断を周知、わからない組合員はいない ▽畑作物の1割を枝豆にできれば、楽になる ▽希望者多数で面積を制限、実績に応じて配分中 ▽直売所を4カ所設置し、職員に「売る姿勢」を ▽愛食フェアへの参加も職員教育の一環 ▽農協塾が好評、職員5人が交代でサポートに |
|||
| 9月13日掲載 | ||||
| 下小路 英男 | 道立中央農業試験場場長 | |||
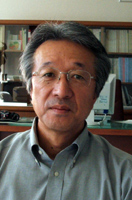 |
☆研究体制の効率化進め、現場の課題に対応 ▽独法化で試験場の自主性が増す ▽基礎研究の重要性を提案していく ▽有機農業の経営評価に着手 ▽北海道で化肥の5割削減厳しい ▽米の高度クリーン化を実証 ▽転換畑の土地改良が課題 ▽公募型の資金増え、北農研との連携深まる ▽地域支援会議設置し、現場の課題対応を充実 |
|||
| 9月6日掲載 | ||||
| 塩谷 和正 | 農林水産省生産局総務課生産政策室長 | |||
 |
☆休止したWTO農業交渉、カギを握るのは― ▽GATT設立はブロック経済化の防止が目的 ▽1995年のUR交渉でWTO体制へ移行 ▽モダリティと譲許表による交渉はURから ▽WTOの意思決定はコンセンサス ▽アメリカの都合で決まった合意期限 ▽アメリカ無視はあり得ないのが現実 ▽対立の三角形、特に頑なだったアメリカ ▽ファスト・トラック延長なら、早期交渉再開も ▽アメリカとEUの不仲、ともにG20に接近 ▽関税率削減、階層方式はUR方式よりも深刻 ▽重要品目も天国にあらず、枠拡大が焦点 |
|||
| 8月30日掲載 | ||||
| 原井 松純 | JAべつかい代表理事組合長 | |||
 |
☆酪農情勢と生乳生産者としての責任 ▽チーズ増産、現実的、有力な選択 ▽量と価格、さらなる選択肢要検討 ▽全道的観点で需給調整施設必要 ▽事故が起きたらすべて回収では無駄 ▽基本技術再確認、放牧推進で所得確保 ▽減産計画は経営見つめなおすチャンス ▽需要期に搾り集中し、目標達成したい ▽後継者はほぼ確保している ▽JA合併は具体的に、慎重に検討 |
|||
| 8月23日掲載 | ||||
| 麻田 信二 | 前北海道副知事 | |||
 |
☆北海道は農業で自立するしかない ▽「農」が創る北海道ライフのすすめ ▽食料問題と環境問題を自分で考える ▽農業ほどやりがいがあることはない、が結論 ▽耕す文化の時代―これからのライフスタイルに ▽独立自尊の二宮尊徳、上杉鷹山に学ぶ ▽農工商一体の考え方は、道民理解につながる ▽いかに他に依存しないでやるか、府県に学ぶ ▽地域ごとの多様な取り組みが元気につながる |
|||
| 8月16日掲載 | ||||
| 植田 晃雄 | JAくしろ丹頂代表理事組合長 | |||
 |
☆4JA合併のメリット発揮で酪農振興 ▽組合員減少の中でJAの支援維持が課題となった ▽当初は5JAでスタート、しかし釧路問題発生 ▽5JAから阿寒町がやむなく離脱 ▽新JA当面の目標販売高100億円 ▽将来は釧路一本化構想へ ▽手数料など合併前に調整済み、給与は段階的に ▽集送乳合理化でメリット発揮 ▽合併契機に機械化作業体系再構築 ▽移転を含めた経営再編も課題に ▽18年度計画枠は未達の可能性も |
|||
| 8月9日掲載 | ||||
| 仲山 浩 | JA平取町代表理事組合長 | |||
 |
☆組合員との密接な関係保ち、複合経営の発展を ▽全量集荷でトマトのブランド化を達成 ▽新選果場で産地パック、付加価値高める ▽長期出荷を含む安定供給が市場評価を獲得 ▽トマトに20億円投資、競合産地の先々を走る ▽出荷最盛期の労力に課題 ▽選果料は必要経費を出荷量で割り返す ▽新規参入、3年間しっかり研修して就農 ▽トマト農家は全員認定農業者 ▽原点を忘れず組合員ともども農協を運営 |
|||
| 8月2日掲載 | ||||
| 仁木 良哉 | 北海道大学名誉教授 | |||
| 酪農学園大学客員教授 | ||||
 |
☆「病気にならない生き方」への科学的反論 ▽新谷氏の牛乳有害論、科学的検証がない ▽カゼインは分解酵素が働きやすい構造 ▽カルシウムと集中的に結合、吸収も良い ▽骨粗しょう症との因果関係、恣意的な論文引用 ▽二重結合少ない乳脂肪、確率的に酸化されにくい ▽市乳で子牛死ぬ―初乳との違い知らない証拠 ▽乳糖不耐性、アジアに多いが、摂取機会の影響も ▽少しずつ飲めば不耐性出にくい研究も ▽完全食品ではないが、極めて有用な食品 |
|||
| 7月26日掲載 | ||||
| 飛田 稔章 | JA道中央会副会長 | |||
 |
☆19年からの新制度導入に向けたバネはできた ▽価格支持制度からの衣替えに難しさ ▽中身をどう理解し、生産活動を継続するか ▽実効性確保に向け、詰めの作業はこれから ▽米の担い手対策が重要、全国的な計画生産を |
|||
| 7月19日掲載 | 渡辺 和義 | 道農政部農業経営局 | ||
| 技術普及課首席普及指導員 | ||||
 |
☆普及事業は人相手、現場の評価が重要 ▽55カ所の普及センターを本所・支所体制に ▽普及指導員への一元化はレベルアップに ▽スペシャリスト、主任普及指導員が引き継ぐ ▽今後も定数削減の可能性、1~2年が勝負 ▽勉強会を通じ、農協や市町村との連携を強化 ▽中央会主導で営農指導力強化、今年は元年 ▽「経営合理性」まで考えた技術普及を ▽世界的に行われている普通の普及事業に戻れ ▽組織を動かすのに10年かかった ▽150重点地域で実証、データを積み上げ ▽成果が出れば文句は出ない ▽マンパワーの支援は手を抜かず、OBも活用 |
|||
| 7月12日掲載 | 宮田 勇 | JA道中央会会長 | ||
| 矢野 征男 | ホクレン会長 | |||
 |
☆再生産可能な水準の交付金を求める 宮田 勇 JA道中央会会長 ▽再生産可能な水準の確保を目標に運動展開 ▽ラミー事務局長に日本の意向伝えることできた ▽農協改革の努力無視した報道は残念 ☆手取り減など課題克服しチーズの振興図る 矢野 征男 ホクレン会長 ▽飲用需要は増加、キャンペーン強化で後押し ▽チーズ増産、手取り乳価低下が課題 ▽価格も上昇しこれからが米チェンの正念場 |
|||
| 7月5日掲載 | ||||
| 石川 文雄 | 株式会社K&K代表取締役 | |||
 |
☆食品残さを活用し、真の地産地消を ▽EM技術を活用、試行錯誤でシステム構築 ▽グランドホテル、JRタワーにシステム導入 ▽三笠のすべての生ごみを400㌧の堆肥に ▽自治体ぐるみの堆肥化をターゲットに ▽残留農薬はゼロ、安全面に自信 ▽市町村と農協との連携が理想 ▽コストかかるも、乾燥処理で発酵促進 ▽契約農家の作物を首都圏生協などに販売 ▽食品残さ活用してこそ地産地消 |
|||
| 「水曜インタビュー」バックナンバー | ||||